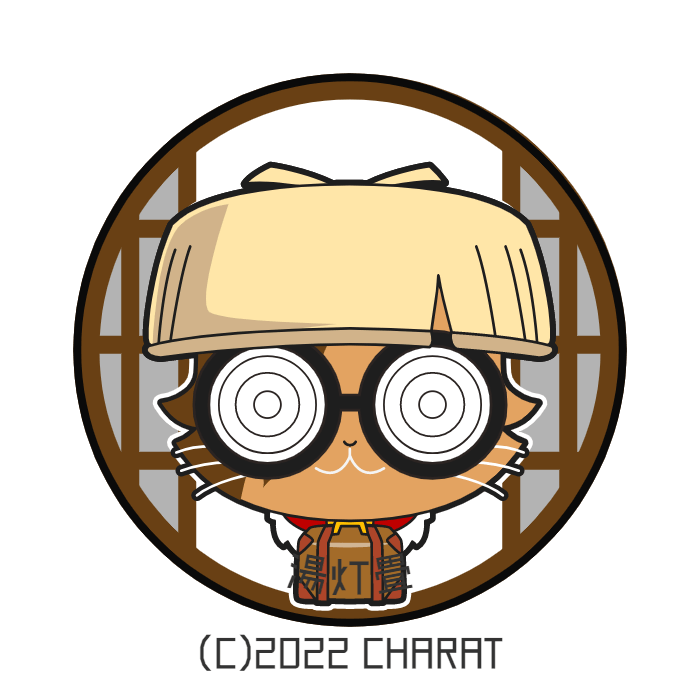雪月花 第二十一夜 湯粥
朝。
囲炉裏の火は、いつもより、早く起こされた。
鍋に米。
刻んだ大根。 大根の葉を、ほんの少し。
白の中に、緑がわずかに。
桶の布をめくる。
湯はまだぬるい。
底に白がわずかに沈んでいる。
鍋に水。
いつもより、少しだけ少なめに。
そこへ、盥の湯を注ぐ。
白はすぐにほどけた。
水と見分けがつかなくなる。
それでも、ゆき姉は目を離さなかった。
煮えるまで、時間がかかる。
火を強くすれば、焦げる。
弱くすれば、煮えない。
ゆき姉は、黙って鍋を見ていた。
はる坊が目を覚ましたのは、その頃だった。
咳が、一つ。
それだけ。
「……いい匂い」
それは、いつもの言葉だった。
けれど―― 今日は、少しだけ違う。
椀に盛る。
白い。 ほとんど、白。
緑が散らされたように、ほんの少し見えるだけ。
「どう?」
はる坊は、すぐには、答えなかった。
匙で、一口。
ゆっくり。
「……あれ?」
もう一口。
「……なんか、いつもより……」
言葉を、探す。
「……食べやすい」
それ以上は、言わなかった。
ゆき姉も、聞かなかった。
熱は、下がらない。
咳も、消えない。
でも、椀は、空になった。
その夜も、湯を汲みに行った。
同じように。
同じだけ。
欲張らず。
次の夜も。
その次の夜も。
何度目かの朝。
はる坊は、椀を見て言った。
「……今日の、ちょっと、美味しくなってる」
それが、気のせいかどうか――
誰にも、分からない。
ゆき姉は、ただ、うなずいた。
湯は、少しずつ、多くなる。
盥を伸ばす腕も、迷わなくなる。
味も、身体も――
まだ、はっきりとは、変わらない。
けれど――
夜ごとに、湯の音が、近くなっていた。
――第二十一夜・了