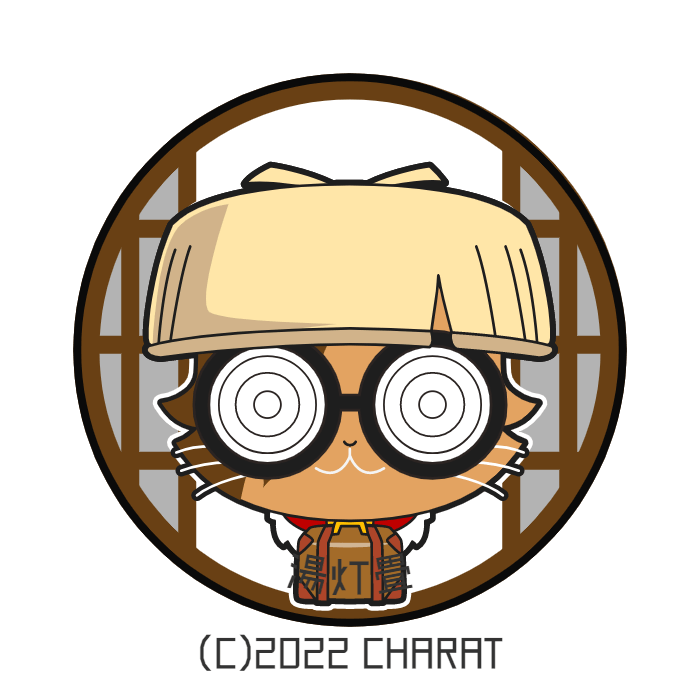雪月花 第二十七夜 母
「……きれいだよね、それ」
ゆき姉の髪を、留めているもの。
銀の、笄。
「前から、つけてたっけ」 「……うん」 「……ふーん、そうだっけ」
それだけ言って、はる坊は、先に行く。
深く、考えている様子はない。
いつもの、調子だった。
けれど、その言葉だけが、残った。
夜。
部屋に戻り、笄を外す。
指に、ひんやりとした重さ。
いつから、身につけていたのか。
はっきりとは、覚えていない。
渡された。
それだけは、覚えている。
理由は、聞かなかった。
——聞かなくても、いいと思っていた。
思い出す。
昔、話したこと。
転んでも、赤くならなかったこと。
怪我をしても、痛みばかりで、血が出なかったこと。
「人には、言わなくていい」
そう、言われた。
深い理由は、聞かなかった。
聞いては、いけない気が、していた。
今夜は、なぜか、気になった。
神社は、もう、人の気配がない。
灯りの下で、帳面が、静かに閉じられる。
「……お爺ちゃん」
声をかけると、わずかに、視線が上がる。
「どうした」
笄を、差し出す。
「これ……どうして、くれたの?」
手に取ると、しばらく、沈黙。
「……そうか」
「……すまない、な」
それだけ言って、視線を落とす。
しばらく、黙ってから、
「これは……形見だ」
昔の話だと、前置きもなく。
吹雪の夜だったこと。
社の前に、籠が、置かれていたこと。
中には、赤子。
その脇に、この笄が、添えられていたこと。
姿は、見えなかった。
声だけが、吹雪の向こうから、聞こえた。
「この子を、お願いします」
名も、そのとき、告げられた。
「雪音を、どうか」
「普通に――育ててやってください」
「私のように、ならぬよう――」
そこまで語られ、言葉が、途切れる。
「どういう人だったのかは、分からん」
「だが」
「母親だったことだけは、確かだ」
笄が、手のひらに、戻される。
胸の奥が、静かに、揺れた。
驚きは、なかった。
噂話。
雪女。
遠くで、聞いたことのある、名前。
笄の冷たさが、指に、残ったまま。
名前だけが、胸に、沈んでいく。
「……私」
声が、かすれる。
「私は……」
遮られない。
答えも、急がされない。
夜風が、社を、通り抜ける。
笄が、かすかに、鳴った。
名は、そこに、置かれていた。
雪音。
それを、どう受け取るかは、まだ、決まらないまま。
――第二十七夜・了