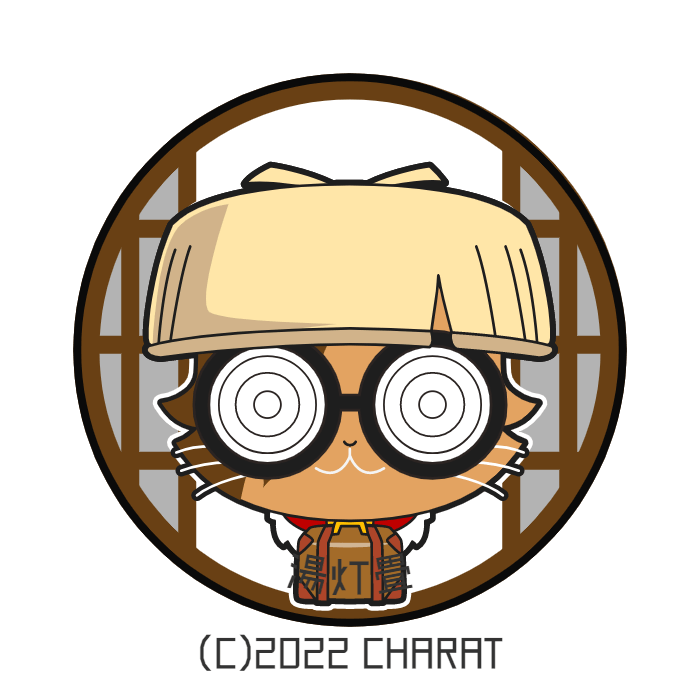雪月花 第十八夜 告白
今日は、客もなく静かな一日だった。
夜。 バー耳枕へ。
黙って座って、無言。
それを見て――
「……いいよ、おごる」
そう言って枕兎から差し出されたのは、深い蒼色の酒、ブルームーン。
一口。
……思わず、ため息が出る。
「あの……」 「ん……」 「女将さん……なんですけど」
グラスを磨きながら、視線を合わせないでいる枕兎。
「やっぱり、あの人は……」 「私に聞かないで」
ぴしゃり。
「私はただ、手伝ってるだけだし」
視線を落としたまま、淡々と。
「でも……」
一拍。
「仕事が手に付かないなら、聞いても良いと思う」 「……」 「とにかく……私の口から言えるわけないから」 「……ですよね」
酒を、ぐいっと呷る。
「その耳」 「……ん?」 「酒猿さんも、湯猫さんも……みんな、耳とか尻尾とか……」 「……」 「何なんですか、一体?」
言い終えて、後悔。
今更聞くのも、野暮なのはわかってる。
でも――
「そりゃ、動物だもん、みんな」
……え?
意外なほど、あっさりだった。
「動……物?」 「私は、見ての通りの兎。前はセンセイのところで飼われてた」
どうやらこの枕兎、かつては開業医の女医に飼われていたのだという。
つまり、ペットの兎。
その先生の話を聞くうち、少々の医療やアロマの知識――
そして自宅にバーがあったおかげで、バーテンダーの知識も身についたのだそう。
湯猫はというと、以前はとある老舗温泉旅館の家猫だったと――
そこで自由に暮らすうち、温泉の知識やレトロな趣味を持ったという。
酒猿は、かつてとある猿軍団に所属して、かなり大掛かりなステージを務めていたのだとか。
団長が大の酒好き宴会好きで、おまけに料理好き。 完全にその性格が乗り移った、と言っているらしい。
そんな素性の違う三匹がたまたま集まって、今はこうして、女将さんの夢である、旅館「雪月花」を手伝っている、というのだが……
「……夢?」 「まあ、それも私の口からは……」
女将さんについては、あまり話したくないらしい。
酒までおごってもらっておいて、これ以上、深入りする気にもなれなかった。
バーを出て。
酔い覚ましに、夜風に当たりに玄関を出る。
月が冴える、冷たい空気。
火照った頬に、心地よい。
「……そうだ」
その足で、裏庭へ。
慰霊碑。
そして、あの――
夢と、いつはる。
今なら、何か――
そこには、女将さんの姿があった。
月照らす雪明かりに浮かぶ、白い姿。
人ならぬ―― 透明な。
まるで、この時を待っていたかのように――
「もう……」
ぽつりと。
「すべてをお伝えするしか、ありません……ね」
女将さんが髪に刺している、銀の笄。
月明かりを受けてか、ぼんやりと光を放ったように――
視界が、滲んでいく。
――第十八夜・了