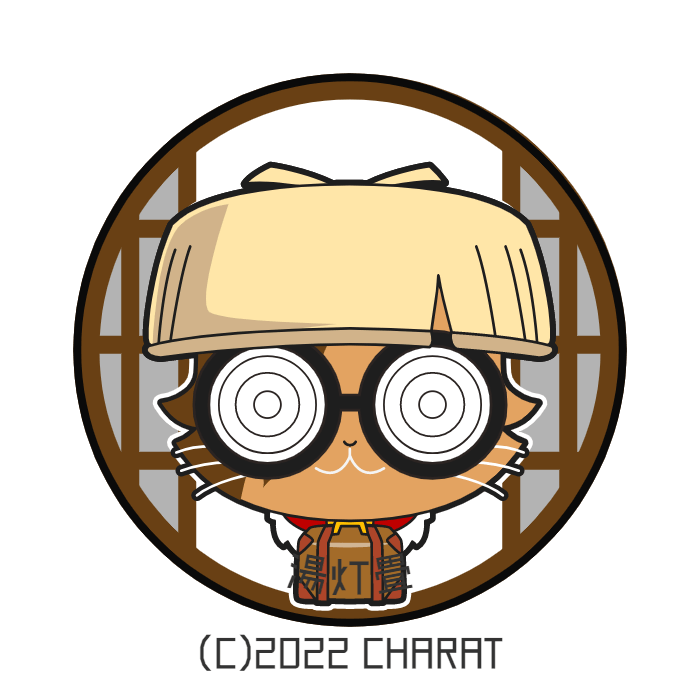雪月花 第三十一夜 雪解け
朝の帳場は、いつもと同じ匂いがした。
味噌と、濡れた廊下と、湯気。
女将さんは、何も言わずに、ゆき姉の前に立つ。
一拍。
それから、ほっとしたように、目を細めた。
「……無事で、よかった」
それだけだった。
叱責もない。 問いただしも、ない。
ゆき姉は、思わず、頭を下げかけて―― 途中で止まる。
女将さんは、それを見て、ふっと息を吐いた。
「今日は、無理しないで」 「出来ることだけ、ゆっくりでいいからね」
母親の声だった。
ゆき姉の胸の奥で、何かが、静かにほどける。
配膳は、普段より一つ少ない。
重い仕事は、自然と、他の仲居に回されている。
誰も、説明しない。
誰も、触れない。
それでも。
「こっちは大丈夫?」 「あとで交代しようか」
声だけは、ちゃんと届く。
ゆき姉は、一つ一つ、頷いて。
「はい」
それだけを、返す。
必要とされる居場所が、ありがたい。
"何事もなかった顔"を、許されているのではなく。
"戻っていい"と、迎え入れられている。
それが、分かる。
今日は早くに、家に帰される。
はる坊は、裏口で待っていた。
声をかける前に、目が合う。
どちらからともなく、歩き出す。
並ぶ。
少し、間を空けて。
沈黙は、重くない。
「……お疲れ様」
はる坊が言う。
「うん」
ゆき姉は、それだけ返す。
少し歩いて、立ち止まる。
「……俺さ」
はる坊は、前を見たまま。
「ゆき姉がいないって聞いたとき、頭、真っ白になってさ」
一拍。
「あの日のこと、ずっと考えてて――」
前を見たまま。
「頼まれなくても、探さずにはいられなくなって」
言い淀む。
「……だから、見つけたとき……正直、腰が抜けそうだった」
小さく、息を吐く。
ゆき姉の肩が、わずかに揺れる。
「……ごめん」
掠れた声。
はる坊は、首を振る。
「謝るとこじゃない」
短く。
「でも――」
一拍。
「いなくなるなんて、……もう、なしだから」
その瞬間。
ゆき姉の中で、張り詰めていたものが、音もなく崩れる。
涙は、出ない。
ただ、息が、楽になる。
春は、確かにここにある。
夜。
隣村の旅籠。
安酒の匂い。
「……ここは、駄目だな」
誰かが言う。
「固いし、ケチだし、ロクに人の話も聞きゃしねえ」
小さく舌打ち。
「ま、いいさ、次がある」
酒をあおって、笑う。
「そういや、聞いたんだけどよ」 「あ?」 「この先の村、温泉があるらしいぜ」 「へえ」 「人もまあ、お人好しばかりだって噂だ」
少し間。
「……じゃあ、明日はそこ行くか」
軽い声。
決めた、というより、流れで、そうなっただけ。
春の夜は、まだ、静かだった。
――第三十一夜・了